うつ病の“イライラする・怒りっぽくなる”という症状で、人間関係を悪くしないポイントとは?
2024/6/14 最終更新
うつ病の症状と言えば気分の落ち込みや意欲の低下などが最初に思
今回はそのなかでも、症状と思われにくい「イライラする」「怒りっぽくなる」「焦りがある」について説明し、イライラして攻撃的になってしまうことなどに、どのように付き合っていけばいいのかもあわせてご紹介したいと思います。
2024/6/14 最終更新
うつ病の症状と言えば気分の落ち込みや意欲の低下などが最初に思
今回はそのなかでも、症状と思われにくい「イライラする」「怒りっぽくなる」「焦りがある」について説明し、イライラして攻撃的になってしまうことなどに、どのように付き合っていけばいいのかもあわせてご紹介したいと思います。
目次

うつ病の症状として代表的なものは“抑うつ”と呼ばれるものです。
具体的には、憂うつな気分、悲しい、気分の落ち込みや悲観的になる、などがあります。
人間ですから、つらいことがあると一時的に落ち込んだり、悲しい気持ちになることは自然な心理です。
しかし、抑うつが一日中、ほぼ毎日、二週間以上継続すると、うつ病が疑われます。
心当たりがある場合は、できるだけ早く受診し、医師の診断を受けてください。
抑うつはうつ病の症状として自覚しやすいものですが、うつ病にはほかにも日常生活に支障をきたす症状があります。
そのひとつが些細なことにも反応し、不機嫌になってしまうイライラ感です。
他人の何気ない態度にも不快感を覚え、強いストレスを感じます。思い通りにいかないとイライラするのが抑えられなかったり、イライラのレベルを超えて強烈な怒りを感じ、攻撃的になってしまう、という症状もあります。
このように、悲しみや気分の落ち込みとは逆に見えるようなイライラや怒りも、うつ病の症状として同時にあらわれることがあります。
気分が落ち込んだり、ものごとに対して悲観的になる、というのは比較的自覚しやすい症状です。対して、普段よりイライラしやすくなっている、怒りっぽくなっている、というのは症状と症状でないものと区別しにくいのかもしれません。
しかし、病気によるイライラや怒りというのは、想像以上につらいものです。
心のなかは、焦りや不安でじりじりと焼けつくようであり、心安らぐこともできません。居ても立っても居られない気分で、常にそわそわし、落ち着きのなさが目立ちます。
思考ばかり空回りして、仕事にも集中力を欠き、予定通り進めることも難しくなります。
そして、自分の感情をコントロールできないために、周囲とのトラブルを招きやすく、対人関係も悪化してしまうという状況になりかねません。
このような症状を抱えている方は、周囲から見ると、いつも不機嫌な怒りっぽい人と誤解されるかもしれませんが、本人は毎日をやり過ごすだけで精いっぱいというしんどさを持っています。
まずは、度を越えたイライラや我慢できないような怒りは、うつ病の症状のひとつであることを理解してもらいたいと思います。

度を超えたイライラや強い怒りはうつ病の症状のひとつであると説明してきました。病気の症状なので、薬物療法(服薬)は効果が期待できる治療法です。
同時に、自分の感情をコントロールするスキルを身につける心理療法も有効です。
昨今『アンガーマネジメント』という言葉が認知され始めています。これは、怒りやイライラを適切に処理し、コントロールする心理トレーニングです。うつ病患者に限らず、職場の対人関係を円滑に進めるために研修で取り入れる企業も増えています。
イライラや怒りの感情を持つこと自体は、人間の自然な心理です。問題になるのは、その感情を持て余したり、対人関係において適切でない表現につながってしまう場合です。
このような状況になると、日常生活に支障が出てきます。
そうならないために、アンガーマネジメントを予防的に取り入れたり、対処法として身につけることが大切です。
ここで、日常生活に支障が出る感情のぶつけ方を例示してみましょう。
ビジネスパーソンが一日の多くを過ごすのは職場です。こんな場面に心当たりはないでしょうか。
怒りを感じた相手を同僚Aとします。Aは要領がよく、いつも仕事を持ち越さず、定時に退社します。
自分は頼まれた仕事を断れないタイプで、気づくと仕事が山積みです。常に多くの案件を抱え、手一杯。今日は夜に約束があるので早く仕事を切り上げたいのですが、明日までに仕上げなければならない書類が残っています。
同僚A「じゃ、時間なので、お先に失礼します」
自分「……お疲れさま」
口ではそう言うものの、終わりそうにない書類を前にして、自分は途方に暮れるばかりです。早く終わらせないと、と焦りも募り、焦るほど集中力がなくなります。「どうしよう、どうしよう」と絶望的な気分になるかもしれません。どうして自分がこんな目にあうのだろうと悲観的になり、強い怒りを覚えます。
「Aはいいよな! 上司から可愛がられてるから、仕事で手抜きをしても、怒られなくて!」
つい心にもない言葉が出てしまいました。周囲の目が冷ややかなことに気づいても取り返しはつきません。後悔し、自責の念に駆られて、ひどく落ち込みました。
落ち込みは続くものの、同僚にイライラしたり、そのイライラをぶつけることもやめられず、職場での対人関係は悪化する一方です。
このような“自分”は珍しくないと思います。共感できる点はたくさんあるでしょう。しかし、この感情の扱い方は適切と言えるでしょうか。
周囲との関係を悪化させ、職場で孤立しかねません。対人関係のトラブルは大きなストレスになります。
自分を責める気持ちは自信喪失につながり、「どうせ自分なんて」と自己卑下することにつながります。
このようなイライラ、怒りの表現は自分にとって不利益しか生みません。
それでもどうしてよいのかわからないので、多くの人は悩み、対処法を身につけたいと望むのです。

イライラや怒りの対処法を『アンガーマネジメント』と呼びますが、いろいろな手法を用い、怒りという感情をおさめます。今回は、アドラー心理学の考え方を紹介します。
怒りを抑えきれないとよく言いますが、これは事実を正しく表現していると言えるでしょうか。
たとえば、先の例で考えてみましょう。“自分”が怒りを抑えきれず、怒鳴り散らしているときに、社長があらわれたとしたら、“自分”はどうしますか?
もしかしたら、なりふり構わず、怒鳴り続けるという人もいるかもしれません。
その一方で、目上の人を前にし、急に態度を変える人もいるかもしれません。
社長に「何かあったのか」と尋ねられたら、突然おとなしくなり「なんでもありません」と答えるかもしれません。もしかしたら、愛想笑いすら浮かべて、社長のご機嫌伺いをすることもあるでしょう。
会社という組織では見られる光景です。
ですが、このとき“自分”の怒りはどこに行ったのでしょうか。
本当に怒りがコントロールできないものならば、こんな風に場面に応じて、怒りを出し入れできないはずです。ところが、人間は往々にして、怒りという感情を使いこなしています。少なくとも、アドラーはそのように考えました。
怒りはマネジメントできるものであるということです。
次に、何のために怒りを爆発させたのかを考えると、今度は“目的”が浮かび上がってきます。
怒りを爆発させることで“自分”にとってメリットがあるわけです。
今回のケースなら、もしかしたら「周囲に、自分のしんどさをわかってほしい」ということかもしれません。要領の悪い自分に対する自己嫌悪かもしれません。目的はひとつではないでしょう。
自分の中にある欲求を満たすために、怒りという感情を使うのです。
このように理解すると、本当は怒りを使う必要がないことがわかってきます。
「今日は大事な約束があるから、手の空いている人は助けてほしい」と伝えることができれていれば、怒りは必要ありませんでした。普段から努力している姿を知っている同僚なら、困ったときには助けてくれるはずです。
自分の要領の悪さを嘆きたい気持ちがあるなら、ノートの一面を使い、その気持ちを書き連ねてもいいかもしれません。自分を客観的に見ることができ、徐々に頭が冷えてきます。
怒りを爆発させ、周囲との関係を悪化させる前に、できることはたくさんあります。
まずは、自分のこころを見つめ、「本当にしたいことは何か」を問いかける習慣をつけていくのがいいでしょう。
そうすれば、不要な怒りは断捨離し、本当に満たしたい欲求にフォーカスすることができるようになります。

イライラや怒りが抑えられず、つい攻撃的になってしまう。
抑えようと頑張っているのに、それができず自己嫌悪してしまうなど、アンガーマネジメントは自身の心のためにも大切です。
リワークセンターRodinaは、休職中の方の復職や、退職後の就職をサポートしています。
利用中に受けられるプログラムは約3,000あり、自身に役立つものを受講できます。
たとえば、イライラへの対処法を学ぶのに有用なプログラムとして下記などがあります。
アンガーマネジメント
認知行動療法
ストレスコーピング
アサーティブトレーニング
疾病理解
またプログラム受講後の変化の一例をご紹介します。
復職後に「変わったね」「怖くなくなった」と言ってもらえた。
感情のコントロールが意識できるようになり、人に受け入れてもらえやすくなった。
どんな時にイライラやストレスが生じやすいかを洗い出し、対処法を考えられたことで、復職後の今に役立っている。
「こんなことでイライラするなんて自分だけかな……」と悩んでいたけど、スタッフさんに共感してもらえて安心できた。
リワークセンターでは、プログラムの無料体験会を開催しています。
怒りの原因となるストレスへの対処法などが学べます。
あなたに合ったプログラム体験会をご案内しますので、まずはお気軽に相談予約フォームからお問い合わせください。
体験前に、リワークセンターがどんなところなのかを知りたい方には資料請求がおすすめです。
今なら復職・就職エピソードbookもプレゼントしています。
こちらの資料請求フォームよりお問い合わせください。
※コラム中の画像は全てイメージです
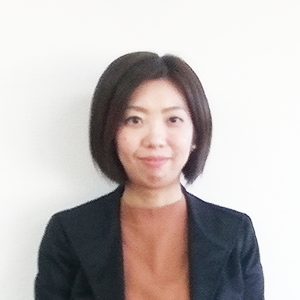
関連コラム