大人の癇癪とは? 特徴や発達障害との関連性、怒りを抑える方法を徹底解説
2025/9/3 最終更新
ついカッとなる癇癪(かんしゃく)で悩んでいませんか。
この記事では、大人の癇癪の具体的な特徴からその背景にあるストレスや発達障害との関係性までを詳しく解説。自分でできるアンガーマネジメントや周囲と協力する方法などを紹介し、悩みを解決するヒントを届けます。
2025/9/3 最終更新
ついカッとなる癇癪(かんしゃく)で悩んでいませんか。
この記事では、大人の癇癪の具体的な特徴からその背景にあるストレスや発達障害との関係性までを詳しく解説。自分でできるアンガーマネジメントや周囲と協力する方法などを紹介し、悩みを解決するヒントを届けます。
病気や障害のこと、暮らしのこと、
お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、
何でもご相談ください。

ささいなことでカッとなり、自分でもコントロールできないほどの激しい怒りに襲われる「癇癪(かんしゃく)」。これは単に怒りっぽい性格ではなく、心身からのサインかもしれません。
大人の癇癪は医学的な診断名ではありませんが、感情のコントロールが一時的にできなくなる状態を指し、これによって自己嫌悪に陥ったり人間関係に支障をきたしたりすることがあります。

癇癪は気質のせいにされがちですが、実際はそうでないことも少なくありません。
その背景にはストレスの蓄積、疲労、睡眠不足といった要因が隠れている可能性があります。疲弊していると感情のコントロールがむずかしくなり、ささいな刺激に過敏に反応してしまうのです。
また発達障害の特性が関係している場合もあり、癇癪はさまざまな要因によって起こる「反応」ととらえることが、解決への第一歩となります。
たびたび癇癪をくり返すと、日常生活に深刻な影響をおよぼします。特に家族や同僚など身近な人との人間関係が悪化し、信頼を失ってしまいかねません。また職場でも感情のコントロールができない人とみなされ、重要な仕事を任せてもらえなくなったり、社会的な信用を失ったりするリスクも考えられます。
なにより癇癪のあとに激しい自己嫌悪や後悔にさいなまれ、自尊心が低下していく悪循環に陥ることもあります。こうした状態は、うつ病などの二次的な精神疾患を引き起こす可能性もはらんでいます。
コントロールがむずかしい怒りの感情も、けっして対処できないわけではありません。
怒りのピークといわれる「6秒」をやり過ごすためのテクニックを中心に、具体的な対処法を7つ紹介します。

怒りがこみ上げてきたら、まずその場から離れるのがもっともシンプルで効果的な方法のひとつです 。
怒りを引き起こした対象や環境から物理的に距離をとることで、冷静さを取り戻すきっかけをつかめます。たとえば「少し頭を冷やしてくる」と伝えて別の部屋に移動したり、トイレに立ったりするだけでもかまいません。この数秒から数分間をやり過ごすことができれば、衝動的な言動を避けられる可能性が高まります。
無理にその場で怒りを抑え込もうとすると、かえって感情が爆発してしまうこともあります。安全な場所に一時的に避難することは、自分自身と相手を守るための有効な手段です。
怒りを感じると、からだは無意識に緊張し、呼吸は浅く速くなります。こうした身体的な反応を意識的にコントロールすることで、心を落ち着かせることができます。深くゆっくりとした呼吸(腹式呼吸)は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果が期待できます。
イライラしてきたと感じたら、深呼吸をゆっくりと数回くり返してみてください。また首や肩を回したり、ぐっと伸びをしたりする簡単なストレッチも、からだの緊張をほぐすのに役立ちます。これらの方法は仕事中や会議の前など、緊張が高まりやすい場面で特におすすめです。
自分の怒りを客観的にとらえることも、感情のコントロールに役立ちます。
怒りを感じたときに「今の怒りレベルは10段階のうちどれくらいだろう」と自分に問いかけてみましょう。まったく怒っていない状態を0、人生最大の怒りを10として点数をつけてみるのです。この作業をおこなうことで、自分の状態を冷静に観察する視点をもつことができます。
「今回はレベル7、かなり強いな」「これはレベル3くらい、やり過ごせそう」などと考えることで、感情と自分との間に距離が生まれ衝動的な行動に走るのを防ぎやすくなります。最初はむずかしく感じるかもしれませんが、習慣にすることで自分の怒りのパターン把握にもつながります。
怒りを引き起こすのは、出来事そのものよりも、その出来事をどうとらえるかという「認知」が大きく影響しています。
たとえば人からあいさつをされなかったときに「無視された」だけではなく、「聞こえなかっただけかもしれない」「なにか考えごとをしていたのかな」といった視点を持つこともできます。
自分のなかに「〜べきだ」という強い思い込みがないか、物事を白黒はっきりさせすぎようとしていないかなど、自分の思考の癖に気づき、別のとらえ方ができないか考えてみましょう。積極的に別のとらえ方を考える癖をつけることで、不要な怒りを減らせます。
自分の怒りを理解するために、怒りを感じたときの状況を記録する「アンガーログ」もおすすめです。
「いつ、どこで、なにに」怒ったかを記録し続けると、自分の怒りの傾向が見えてきます。たとえば「月曜の朝はいつもイライラしている」「特定の人の発言に過剰に反応してしまう」といったパターンがわかれば、あらかじめ対策を立てることが可能になります。
またこういった客観的な記録は、カウンセリングなどの専門的なサポートを受ける際にも、自分の状態を正確に伝えるための貴重な資料です。
癇癪や怒りのコントロールの問題は、日々の生活習慣が大きく影響しています。特に睡眠不足は脳の機能を低下させ、感情のコントロールを困難にする大きな要因です。まずは、質の良い睡眠をじゅうぶんにとることを最優先に心がけましょう。
また栄養バランスの取れた食事や適度な運動も、精神的な安定を保つためには欠かせません。こうした基本的な生活習慣を整えることは、感情の波を穏やかにするための土台となります。一時的なテクニックだけでなく、根本的な対策として生活を見直してみましょう。
言葉にするのがむずかしい複雑な怒りは、創造的な活動を通じて表現するのも有効な手段です。
強い怒りは言葉にすると相手を傷つける恐れから、口に出すのをためらってしまうことがあります。そんなときは、感じたことを文章に書きなぐる、絵を描く、楽器を演奏するなど、心のなかのモヤモヤを外に吐き出してみましょう。
大切なのは作品の上手い下手ではありません。誰かに見せる必要もなく、抑圧された感情を安全な形で外に出し「形」として客観的に見つめること自体が、心を整理し冷静さを取り戻すための大きな助けとなります。
癇癪は、自分だけで抱え込む必要はありません。信頼できる周囲の人の理解と協力を得ることも、状況の改善につながります。
相手への配慮を忘れずに、上手に連携しながら癇癪をコントロールしていく方法を紹介します。

癇癪を起こしてしまう可能性があることを、身近で信頼できる人に誠実に伝えておくのは方法のひとつです。そのうえで「こういう状況になると怒りを感じやすい」「イライラし始めたら、こんなサインが出るかもしれない」といった、自分の怒りの引き金(トリガー)や初期症状を具体的に共有しておきましょう。
たとえば「疲れているときに話しかけられると、ついカッとなってしまう」「黙りこんでしまったら、少しそっとしておいてほしい」などと伝えておくことで、相手も無用な衝突を避けやすくなり、いざというときに冷静に対応しやすくなります。
癇癪が起きそうになったときや、起きてしまったあとの対処法を、あらかじめ周囲の人と話し合って決めておくことも大切です。たとえば「カッとなったら、一度ひとりで別の部屋にいく」というルールを家族と共有しておくことで、突然その場を離れても追いかけたり問い詰めたりされずに済みます。
また「10分間はそっとしておいてほしい」「落ち着いたら、自分から話しかける」など、クールダウン後のコミュニケーション方法についても決めておくとお互いに安心して過ごせます。
当事者だけでは解決がむずかしい場合や、家族や周囲の人たちとの関係がすでに悪化してしまっている場合には、カウンセラーなどの専門家を交えて話し合うことを検討しましょう。
専門家が第三者として間に入ることで、感情的になりがちな話し合いを冷静に進めることができます。カウンセリングの場では、本人の状態を専門家の言葉で家族に説明してもらえたり、家族のほうもどう接すればよいのか具体的なアドバイスを受けられたりします。
専門家のサポートを得ることはけっして特別なことではなく、一般的な選択肢のひとつなのです。
大人の癇癪の背景には、発達障害の特性が隠れていることがあります。
発達障害は生まれつきの脳機能の発達のかたよりによるもので、大人になってから困難を感じ、はじめて自分の特性に気づくケースも少なくありません。
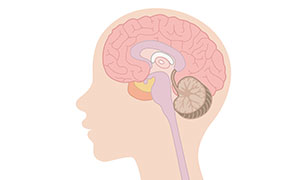
自閉スペクトラム症(ASD)は「対人関係や社会的なコミュニケーションの困難」と「限定された興味やこだわり、感覚のかたより」といった特性をもつ発達障害です。
ASDのある人は、相手の表情や声のトーンから感情を読み取ったり、場の空気を読んだりすることが苦手な場合があります。また自分の気持ちや考えを言葉で的確に表現するのがむずかしいこともあり、そうしたコミュニケーションの困難さから、誤解やフラストレーションを生んでしまい怒りとして表出することがあります。
さらにASDの特性である「こだわり」や「ルーティンの重視」も癇癪と関係します。たとえば決まっていた予定が急に変更になったり、自分の手順を乱されたりすると、強い不安やパニックに陥り、それが癇癪として現れることがあります。
また音や光、匂い、肌触りといった特定の感覚刺激に非常に敏感な「感覚過敏」も大きなストレス源となり、怒りの引き金になることがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)は「不注意」「多動性」「衝動性」の3つを主な特性とする発達障害です。
このなかで、特に大人の癇癪と深く関わっているのが「衝動性」です。ADHDのある人は、感情がわきあがったときに、それをいったん保持して考えるよりも先に、衝動的に言葉や行動として表に出てしまう傾向があります。そのためささいなきっかけでカッとなり、あとさき考えずに怒りを爆発させてしまうことがあるのです。本人に悪気はなく、怒鳴ったあとですぐに「言い過ぎた」と後悔することも多いのですが、多くの場合は感情のブレーキが利きにくい状態といえます。
また「不注意」の特性から仕事でミスをくり返してしまったり、約束を忘れてしまったりすることで、周囲から叱責される機会が多くなりがちです。そうしたストレスの蓄積が自己肯定感の低下をまねき、結果として怒りっぽさにつながっているケースもあります。
一概に断定することはできませんが、幼少期の養育環境が癇癪に影響をおよぼす可能性は指摘されています。たとえば子ども時代に自分の感情を安心して表現できる環境がなかった場合、感情を適切に処理したり伝えたりするスキルが育ちにくいことがあります。親から「怒るのは悪いことだ」などと感情を抑圧されて育つと、大人になってからもため込んだ感情がコントロールできない形で爆発してしまうことがあります。
また親自身が感情のコントロールに問題を抱えており、子どもに対して日常的に怒鳴るような環境で育った場合、子どもはそれをコミュニケーションのモデルとして学習してしまいがちです。ただしこれらはあくまで可能性のひとつであり、すべてのケースにあてはまるわけではありません。重要なのは、過去の環境に縛られることなく、現在の自分がどうすれば生きやすくなるかを考え、これからのために適切な対処法を学んでいくことです。

大人になってから癇癪が始まった場合は、仕事上の責任、複雑な人間関係、ライフスタイルの変化といった、大人特有のストレスの蓄積が原因かもしれません。若いころは乗り越えられたストレスでも、慢性的な疲労や睡眠不足が重なると感情をコントロールする心の余裕がなくなってしまいます。それによって自分でも気づかないうちに許容量を超えてしまい、ため込まれた感情が怒りとしてあふれ出してしまう可能性があります。
まず大切なのは自分の安全を確保し、冷静に対応することです。相手が激しく興奮しているときに、議論や説得を試みるのは避けましょう。相手を刺激せず「少し時間をおこう」などと声をかけ、可能であれば静かにその場を離れて距離を置くのが賢明です。怒りがおさまりお互いが冷静になってから、なにが問題だったのかを話し合う時間をもつようにしてください。 一対一で話し合う場合には、関係性によりますが、安全性の観点から個室は避けて落ち着いたオープンなスペースがお勧めです。また、お互いに落ち着いて話し合うために信頼できる第三者と一緒に話すことも有効です。
大人の癇癪で受診を考える場合、まずは精神科や心療内科への相談をおすすめします。ストレスやうつ、不安障害、あるいは発達障害といった背景にある心の問題について相談でき、適切な治療やカウンセリングにつなげることができます。また女性でホルモンバランスの乱れが気になる場合は、婦人科への相談も有効です。どの科にかかればよいか迷う場合はまずかかりつけ医に相談し、適切な専門科を紹介してもらうのもよいでしょう。
大人の癇癪は本人にとっても周りの人にとってもつらいものですが、けっして改善できないわけではありません。
「性格の問題だから」とひとりで抱え込まず、まずはその背景に目を向けてみましょう。すぐカッとなってしまう背景には、自分でも気づかないストレスや疲労、睡眠不足といった心身のサインのほか、生まれつきの特性が隠れていることもあります。
適切な対処法を学び、ときには専門家に相談することも、穏やかな毎日を取り戻すための大切な一歩です。
※コラム中の画像は全てイメージです
病気や障害のこと、暮らしのこと、
お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、
何でもご相談ください。


