過集中とは? ADHD・ASDとの関係性や特徴・対策を解説
周りの音が聞こえなくなるほど作業に集中してしまう「過集中」。
この記事では過集中の強みと困りごとという両面性、そしてADHDやASDなど発達障害との関係について解説します。過集中をコントロールするための対策や特性を活かす方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
周りの音が聞こえなくなるほど作業に集中してしまう「過集中」。
この記事では過集中の強みと困りごとという両面性、そしてADHDやASDなど発達障害との関係について解説します。過集中をコントロールするための対策や特性を活かす方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
病気や障害のこと、暮らしのこと、
お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、
何でもご相談ください。


過集中とは、自分の好きなことや興味のあることに対して周りが見えなくなるほど極度に集中している状態を指します。これは単に「集中力が高い」状態とは異なり、集中力のオン・オフを自分で制御することが難しいという点が顕著です。
たとえば作業に没頭するあまり食事や睡眠を忘れてしまったり、話しかけられてもまったく気づかなかったりということも少なくありません。本人の意思とは関係なく、ひとつのことに注意が向きすぎてしまい、切り替えが困難になる状態が過集中と呼ばれます。
過集中には
生産性の高さ
アウトプットの質
学習力の向上
といった強みと、
日常生活への支障
健康の悪化
人間関係への影響
といった困りごとの、両方の側面を持っています。これらを理解し、うまくバランスをとることが大切です。

過集中の強みは、興味のある対象に発揮される驚異的な集中力と生産性です。一度集中モードに入ると他のことや疲れを忘れて長時間没頭できるため、短時間で質の高い成果を生み出すことができます。この状態はアスリートなどが最高のパフォーマンスを発揮する、いわゆる「ゾーン」に入った状態に近いといわれます。
この特性は、専門的な知識やスキルを深く追求するうえで大きな強みとなります。たとえばプログラマー、デザイナー、研究者、作家といった、ひとりで深く没頭できる専門職ではその能力を存分に発揮できる可能性があります。過集中はコントロールできれば、他の人に真似のできない大きな成果を生み出すことにもつながるのです。
しかし過集中は、良い点だけではありません。もっとも深刻なのは、心身の健康への影響です。食事や睡眠を忘れて体調を崩したり、休憩をとらずに過労状態になったりと、無意識に自分を酷使してしまうことがよくみられます。日常生活や社会生活においても、時間を忘れて約束に遅刻したり他の家事やタスクがまったく手につかなくなったりします。また集中しているときに話しかけられてもまったく気づかず、人間関係のトラブルに発展することも少なくありません。仕事では自分の興味がある作業に没頭してしまい、締め切りのある重要な仕事が後回しになるなど、優先順位の管理が難しくなります。また興味のないことにはまったく集中できず、集中力の極端なむらが出やすいのも困りごとです。さらに動画視聴やインターネットでの情報収集、投資など特定の対象にのめり込みすぎて依存的になってしまうリスクも指摘されています。
過集中は、発達障害の正式な診断基準に含まれる症状ではありません。しかしADHDの「注意力の制御の困難さ」や、ASDの「興味の限定やこだわり」といった特性が、過集中を引き起こす背景になっていると考えられています。
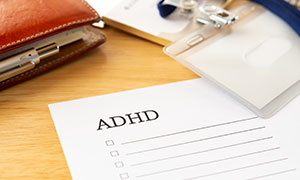
ADHD(注意欠如・多動性障害)は、主に「不注意」と「多動性・衝動性」を特性とする発達障害です。
一般的に、ADHDの不注意は「集中力がない」と誤解されがちですが、実際は「注意をコントロールすることが難しい」状態を指します。そのコントロールの難しさが、ひとつの対象に注意が過度に向いてしまう「過集中」と、注意が散漫になってしまう「不注意」という、一見正反対に見える状態の両方を引き起こします。たとえば興味のない授業や会議では集中できない(不注意)一方で、好きなゲームや趣味には時間を忘れて没頭する(過集中)ということが起こります。
また多動性・衝動性も過集中と無関係ではありません。じっとしていられないといった動きは、脳が刺激を求めている行動とも考えられており、刺激的な対象を見つけるとそこに注意のすべてが注がれます。
このように注意散漫に見える状態と過度に集中する状態は、どちらもADHDの特性に起因する表裏一体の現象といえるでしょう。
ASD(自閉スペクトラム症)は「対人コミュニケーションの困難さ」と「特定の分野への強い関心」を特性とする発達障害です。この特定分野への強い関心が、過集中と深く結びつきます。
ASDと診断された人は、自分が興味を持ったものごとに対して驚異的な集中力を発揮し、膨大な知識を蓄えることがあります。興味の対象が仕事や学業などと結びついた場合はその分野の専門家として高く評価されることがある一方で、興味の対象をなかなか切り替えられない、他のやるべき活動との両立が難しいといった困りごとにつながる場合もあります。
なおADHDとASDは併存することも多く、その場合は両方の特性が影響し合って、より複雑な形で過集中が現れることもあります。
過集中の対策には、その特性を理解しコントロールするという視点が大切です。
特に、
過集中を防ぐ:周囲の協力や工夫で、生活への支障や負担を減らす
過集中を活かす:環境を整え、仕事や学習の強みとして役立てる
といったアプローチが求められます。

過集中によるデメリットを防ぐには、意識的に集中を中断させる工夫が有効です。
もっとも手軽で効果的なのは、アラームやタイマーの活用です。「45分作業して15分休む」のように時間を区切る(ポモドーロテクニック)、「〇時になったら食事をとる」など行動の切り替えのきっかけとして音で知らせるようにします。スマートウォッチのタイマー機能や、ポモドーロタイマーアプリの活用も有効です。
職場や家庭では、あらかじめ周囲の人に自分の特性を伝えておくことが大切です。「集中すると声が聞こえなくなるので、肩を叩いて合図してください」など、具体的な協力をお願いしておくとトラブルを防ぎやすくなります。
またこまめな栄養・水分補給も欠かせません。集中し始めると飲食を忘れがちになるため、作業を始める前に、飲み物や手軽に食べられるものを机の上に用意しておくとよいでしょう。ToDoリストを作成してやるべきことや優先順位を可視化するのも有効です。
過集中という特性を活かすには、自分の興味・関心と、過集中しやすい環境を理解してコントロールすることが大きな強みにつながります。
まず、過集中を強みとして発揮できる職業や役割を考えることが有効です。たとえばプログラミング、デザイン、研究など、ひとりで深く没頭でき専門性が求められる仕事は特性とマッチしやすいでしょう。逆に、頻繁に電話対応や来客対応が求められるようなマルチタスクの多い職場は、集中が中断されやすくストレスになる可能性があります。
職場環境を選ぶ際には、個人の裁量権が大きく自分のペースで仕事を進めやすいといった視点に注目すると、過集中をコントロールしやすい働き方につながるでしょう。
過集中はADHDなど発達障害の特性とも関連し、驚異的な生産性という強みと、心身の不調といった困りごとの両面性を持ちます。大切なのは、過集中をなくすのではなく上手くコントロールすることです。タイマー活用でデメリットを防ぎ、得意な仕事で強みを活かすといった工夫を重ねることが、集中力との上手な付き合い方につながります。自分の特性を正しく理解し、自分に合った方法を見つけることがよりよい生活への第一歩です。

ADHDの人は、脳の機能的な特性から「注意をコントロールすること」が苦手です。そのため注意が散漫になる「不注意」と、逆にひとつのことに注意が固定されてしまう「過集中」の、相反する二つの性質が起こりやすくなります。
まずは、自分自身の特性を客観的に伝えることが大切です。「集中すると話を聞き逃してしまう」など、具体的な状況を説明しましょう。そのうえで「重要な用件はメモで伝えてもらえると助かる」など具体的な協力方法をお願いすることで、誤解を防ぐことにつながります。
※コラム中の画像は全てイメージです
病気や障害のこと、暮らしのこと、
お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、
何でもご相談ください。


